楽器屋さんで試奏する時って何を弾いたら良いかわからないことありますよね。
僕も何を弾いたら良いかわからないことがよくありました。
店員さんや周りのお客さんがいる中だと変に緊張して、「こういうの弾いてみよう」とアイディアが出てこなかったりもしますよね。
今回はそんな時に役立つ、試奏の時に役立つ簡単なギターのフレーズを紹介します。
試奏で使う時のポイント
試奏する時はチェックポイントを決めて行うと良いです。
例えば、「このフレーズは音の伸び方を確認する時に使う」「このフレーズはこれから弾くギターがカッティングに合うかどうかを確認する時に使う」などです。
そういったチェックポイントを設けることで、そのギターが自分に合っているのかどうかを見極めることができます。
普段からギターを弾いている時に「もう少しこういうところが欲しい」ということをメモしておけば、試奏の時もこれを弾こうと決まってくると思います。
楽器店で試奏したいアコースティックギターのカッコいいフレーズ10選
楽器店で試奏したいアコースティックギターのカッコいいフレーズ10選
今回は渋谷の老舗ギターショップBlue-Gさんにご協力いただいて、試奏フレーズの動画撮影を行いました。
アットホームなギターショップで、訪れる方は初心者から上級者、コレクターまで大人気のショップです。
店長の三上さんのインタビュー動画もあるのでぜひみてください!
それでは紹介していきます!
01. Change The World(Eric Clapton)
1996年に発表された、Eric Claptonの楽曲です。アコースティックギターを弾いている人に大人気の曲です。
最初の部分のコードチェンジも簡単なので、初心者におすすめです。
左手のハンマリングフレーズは人差し指の先端でしっかりハンマリングすると良いです。
指を立ててハンマリングをすることで、弦に力が加わり安くなります。
右手のパターンは特に決めて弾かなくても大丈夫です。
ゆっくり音の伸び方を確かめながら弾いても良いし、リズミカルに弾いても良いですね。
Bluesのリックを覚えて、コード進行の合間に入れるととてもカッコ良いですよ。
その際は、コードのストロークやアルぺジオはしっかり弾かなくても大丈夫です。
ちょっとコードを鳴らして、単音弾きということを繰り返していくと良いです。
この進行は開放弦を多用しているので、そのギターの特性を試す時に使えます。

ギター本来の持ち味は開放弦を鳴らした時に出やすいです!
使用ギター:Gibson J-45(1953)
02. 定番Bluesバッキング(Key=E)
Bluesの定番のバッキングです。
12小節のパターンで紹介しているのですが、12小節きっちり弾かなくても良いです。
12小節のパターンはセッションする時などに役立つので、紹介しています。
僕の場合、ちょっとギター弾いてと言われた時など、ショートバージョンでBluesを弾いたりします。
その際に、バッキングのパターンにリックを加えて演奏します。

このバッキングパターンを身体で覚えておけば、リックも簡単に埋め込みやすくなります。
使用ギター:Gibson J-35 Opaque Blonde(1942)
03. ドライフラワー(優里)
2020年に発表された、優里の楽曲です。
シンプルなコード進行で構成されていますが、特定の音を残してコードチェンジをするといった工夫がされており、初心者でも簡単に、おしゃれに弾けるようになっています。
途中でハンマリングプリングのフレーズがあるのですが、「ハンマリング」と「プリング」に分けて演奏すると良いです。
最初はゆっくりハンマリングして、プリングしてを繰り返します。
両方ともうまくできるようになってきたら、スピードを上げていきましょう。
ストロークからいきなり単音弾きになるので、右手のピッキング位置が狙いにくいですが、ストロークを弾いたら一旦止めて、単音弾きという風に切り分けると良いです。
コードストロークした時にどんな音が鳴るかを確かめる時にこの進行を使うと良いです。

特に最初のコードのCadd9は押弦と開放弦のバランスが良いので、コードの鳴りを確かめるにはちょうど良いです。
使用ギター:Martin D-28(1957)
04. E7(+9)でファンクカッティング
定番のファンクカッティングのパターンです。
単純なパターンだけど、かっこよく聴かせられる奏法の代表です!
僕はギターをもってカッティングやろうかなと思うと、とりあえずこのパターンを弾いてみたりします。
難しそうに聴こえますが、本当に簡単です。
右手のストロークはずっと同じパターンで、左手を押さえたり、放したりするだけです。
ブラッシングする時に左手の押弦を緩めるのですが、指板から離れすぎてしまうと、雑音がなってしまいます。軽く緩める程度にしましょう。
慣れてきたらリフを入れたりして、装飾を加えていきましょう。
チャカチャカとブラッシングすることと、コードストロークを交互に行うこのパターンは箱鳴りを確かめる時に使います。

ブラッシング時に音がこもるギターはフィンガーピッキングに向いているのかなと、考えたりします。
使用ギター:Martin 000-28(1955)
05. One More Time One More Chance(山崎まさよし)
1997年に発表された、山崎まさよしの楽曲です。
こちらもアコースティックギターを弾いているギタリストに大人気の曲です。
アコースティックギターを持ったら弾きたくなるフレーズですよね。
右手はフィンガーピッキングで弾いています。
高音弦をメインにした繊細なフィンガーピッキングです。
普段あまり使わないような左手の動きをしますが、「このコードの時にこの押さえ方をしている」と覚えておけば、他の曲でも使えます。
違うボイシングでコードの構成を覚えているということなので、覚えておけばコードのレパートリーになります。
このような理論で、例えばJAZZのコンピングなどでは、同じコードでもボイシングの違う押さえ方を多用して音の広がりを表現します。こういう考え方はソロギターにも使えるので、とても重要度が高いです。

フィンガーピッキングに合うスタイルかどうかや、ハイフレットの音の響きを確かめる時に使えるフレーズです。
使用ギター:Gibson J-45(1953)
06. 空も飛べるはず(スピッツ)
1994年に発表された、スピッツの楽曲です。
これは学校の教科書にも載っているほど有名な楽曲ですね。
シンプルなコード進行に優しいメロディーで、印象深いです。
右手のストロークも簡単なので、よく初心者向けの楽曲としておすすめされている楽曲です。
まだギターをはじめたばかりの方はまず、左手のコード一つを覚えて、右手のストロークに挑戦してみてください。
右手のストロークが安定してきたらコードチェンジをしていきます。
最初にコードを覚えてからストロークをするという方が多いですが、それよりも右手を自動的に動かせるようになることがとても重要です。
右手が無意識に動かせるようになれば左手にも集中ができます。
ストローク後にアルペジオのフレーズがありますが、左手はほとんど指を動かさなくて良いフレーズなので、ゆっくりフレーズの仕組みを理解しながら練習してください。
右手はピック弾きで弾く場合はオルタネイトピッキングで弾いた方が効率が良いです。
この曲は、コードストロークとアルペジオを演奏した時にどのようにギターが鳴るかを確かめる時に使うと良いです。

ストロークとアルペジオだと音量差がありますが、その差が出にくいギターだと一本で色々と表現ができますね。
使用ギター:Pre-War Guitars OM-18 Amber(2019)
07. 丸の内サディスティック(椎名 林檎)
1999年に発表された、椎名 林檎の楽曲です。
よくオシャレ進行と呼ばれているコード進行です。
いろんな曲で使われている進行なので、覚えておくと便利です。
左手の動きは次のコードに関連して動くので、指の切り替えが楽です。
同じ弦でフレットが移動するだけという動きを見つけて、効率よくコードチェンジをしていきましょう。
右手はシンプルなアルぺジオで弾いても良いし、パーカッシブに弾いても良いですね。
右手のパターンは自由に弾いてOKです。「音が鳴ればいいよね」という感覚でやってみましょう。
開放弦を使わないコードパターンを弾いた時に、音が詰まらないかどうかを確認する時に使います。

左手の運指がしやすいかどうかを確かめる時にも有効ですね。
使用ギター:Echizen Guitars R-1(2014)
08. 車の中でかくれてキスをしよう(Mr.Children)
1992年に発表された、Mr.Childrenの楽曲です。
このコードは半音で音が当たっているので、不思議な感じがしますね。
コードチェンジはビックリするくらい簡単です。
人差し指を上げたり下げたりするだけです。
これだけで、こんなにコードの表情を変えられるのはすごいことですよね。
コード進行はGM7とEm7です。
上記のコードが出てきた場合は、このボイシングに変えられるということなので、ちょっと雰囲気を変えたい時にこのコードに変換すると、オシャレなアレンジになることが多いです。
特に弾き語りの時はよく使います。
開放弦が多いので、そのギターの特性を知る時に使います。

半音で当たった時の「音の揺れ」はギターの個性が出やすいので聴き比べてみてください!
使用ギター:Somogyi OM(1996)
09. What’s Going On(Marvin Gaye)
1971年に発表された、Marvin Gayeの楽曲です。
What’s Going Onの一部のコード進行を使用しています。
1度と6度のコードを行ったり来たりするコード進行です。
個人的にとても好きなコード進行です。
1度と6度なので、平行調ということになりますね。
2コードというシンプルな構成なので、コードをいろいろアレンジして弾いてみると楽しいです。
EM7はEM7(9)に替えてみたりE69に変えてみたりとメジャー系のコードにテンションを足したものを色々試してみてください。
C#m7はC#m7(9)に替えたりします。
ハイフレットでコードを弾いた時にどんな音が鳴るのかを試す時に使います。

ハイフレットで弾くと音が詰まりやすいですが、良いギターはストレートに抜けてくれます。
使用ギター:Martin D-18(1941)
10. コードバッキング(2-5-1進行)
Cダイアトニックコードの2度、5度、1度のコードです。
2-5-1は重要な要素が詰まったコード進行なので、動き方を覚えておくと便利です。
また軽くジャムセッションする時に2-5-1を使うことも多いです。
同じ形でフレットを移動すれば、違うキーに適用できますので、ぜひこちらの動きを覚えてください。
サブドミナント – ドミナント – トニックという構成になっており、重要なコードファンクションが全て揃ってます。
ここから発展させて曲を作ったりします。
各コードにテンションをつけてオシャレにアレンジしても良いですね。
例えばDm7→Dm7(9)、G7→G7(13) or G7(-13)、CM7→CM7(9)といった感じです。

開放弦を使わないコード進行の響きを確かめる時に使います。
使用ギター:Martin 00-45(1976)
番外編 カッコいいチューニングの方法
チューナーを使わないチューニング方法です。
基準となる弦の音を合わせたら、チューナーを使わなくてもチューニングができます。
僕は5弦を440Hzに合わせてから他の弦をチューニングしていきます。
440HzはAの音です。チューナーでチューニングする時に5弦は「A」と表示されますね。
また、POPSの基準は5弦が440Hzですが、ジャンルやアレンジによって、Hzが前後する場合があります。
例えば441Hzだったり、438Hzなどです。
基準となる弦に合わせていくので、その弦のHzに沿ったチューニングになっていきます。
POPSのチューニングは、5弦を440Hzに合わせてから、各弦をチューニングすると良いです。
耳でチューニングできるようになると、とても楽です。
ですが、耳に頼りすぎても良くないので、たまには耳のチューニングもしてあげると良いです。

音叉やチューナーに音を出す機能があれば、440Hzの音を聴いて聴感を合わせてください。
使用ギター:Sergei de Jonge OM(2003)
まとめ
いかがでしたでしょうか?
試奏する時は「このフレーズを弾く」と決めていくと、何を弾けば良いか迷うこともなくなりますね。
ギターはいろんな種類を弾いて自分に合うギターを見つけた方が上達も早くなりますので、遠慮せずに楽器屋さんで試奏してください。
試奏する時は借り物のギターなので、くれぐれも丁寧に扱うようにしてくださいね!

今回、ご協力いただいた渋谷のBlue-Gさんはとても居心地の良い、ギター好きが集まる素敵なお店ですので、ぜひ遊びにいってください!
[nlink url=”https://koujun.ac/lesson/phrases-for-testplaying-001/”]
[nlink url=”https://koujun.ac/lesson/phrases-for-testplaying-002/”]
[nlink url=”https://koujun.ac/lesson/phrases-for-testplaying-003/”]
[nlink url=”https://koujun.ac/lesson/phrases-for-testplaying-004/”]
[nlink url=”https://koujun.ac/lesson/phrases-for-testplaying-005/”]
[nlink url=”https://koujun.ac/lesson/phrases-for-testplaying-006/”]
[nlink url=”https://koujun.ac/lesson/phrases-for-testplaying-007/”]
[nlink url=”https://koujun.ac/lesson/phrases-for-testplaying-008/”]
[nlink url=”https://koujun.ac/lesson/phrases-for-testplaying-009/”]
[nlink url=”https://koujun.ac/lesson/phrases-for-testplaying-010/”]
[nlink url=”https://koujun.ac/lesson/phrases-for-testplaying-extra/”]



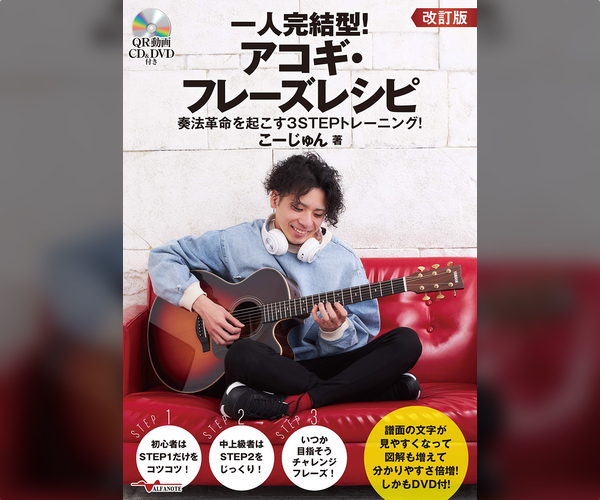
[…] 楽器店で試奏したいBluesフレーズの解説と弾き方 […]